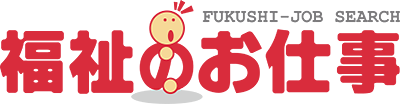welなが(ふくしのお仕事ステーション)のキャリア支援専門員は、県内の高校・専門学校・大学を訪問し、福祉の仕事に関する講話や求職登録、イベントの案内等を行っています。(令和7年4月から9月までで23校を訪問)
そこで聞き取った、学生の就活状況をレポートします。
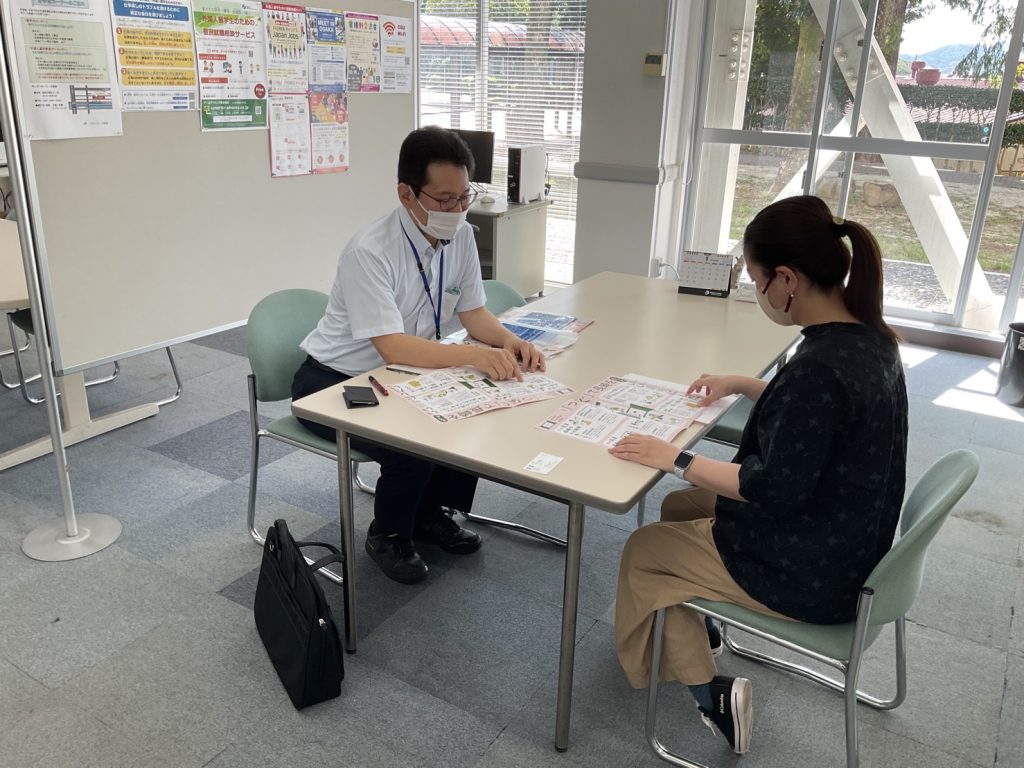
●学生の就活方法
学校に提出された求人や、実習先、マイナビやリクナビ、indeed等のネットやSNSを活用して就活しています。
「様々な求人媒体があり、情報に振り回されている学生も多いようです。ですから効率(タイパ)重視の就活ニーズがありますね。ネットで求人検索から応募までできるので、大学生は、学校のキャリアセンターを利用せず就活している人や、利用している人も応募先を絞り込んだ上で相談に来ることが多いようです。」(下田キャリア支援専門員)
●学生が重視している求人項目
「給与や福利厚生だけでなく、施設の雰囲気や職場環境、人間関係、法人の方針など様々な要因から求人を選んでおり、安全・安心を重視する傾向もあります。」(酒井キャリア支援専門員)
求人票やウェブサイトの充実はもちろんのこと、それだけでは伝わらない部分を補っていく必要があります。より職場の雰囲気を伝えやすいSNSでの情報発信は効果があると推測できます。
●学生の意識の変化
コロナ禍以降、給料面をシビアに見る学生が増え、福祉分野を望む学生が減少傾向にあるようです。学校側も過去に実習先とトラブルがあり、実習に参加する要件を厳しくしたところ、福祉を目指す学生の質が高くなっているという所もありました。なお、就職先を実習先に決める学生も多く、県外希望者がいないという学校もありました。特に自宅から通えるところを希望する傾向にあるようです。(下田キャリア支援専門員)
効率(タイパ)重視の就活ニーズがある一方で、面接はオンラインではなく対面を希望する学生が多いとの声もありました。学校側もコロナ禍以降、合同面談会ではなく、定期的に施設・事業所を招いて個別面談会を実施しているようです。施設で働く卒業生が面談することで学生も参加しやすいようです。(酒井キャリア支援専門員)
●最後に
今回は学生の就活状況についてレポートしましたが、就活には様々な媒体やツールがあり、求職者のニーズは多様化しています。現在本会では、求職者・求人者を対象としたアンケート調査を実施しています。結果を基に今後の事業を展開していきます。お手数をおかけしますが、下記から回答にご協力をお願いいたします。(12/19〆切)